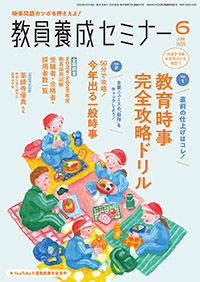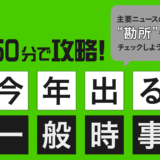POINT解説①「第3次学校安全の推進に関する計画」について
「学校安全の推進に関する計画」は、学校保健安全法第3条第2項に基づき国が策定する計画です。「第3次」は2022年3月に閣議決定され、2022~2026年の5年間の計画を示しています。
Ⅰ 総論
2.施策の基本的な方向性
これまでの取組や課題を踏まえ、第3次計画期間において取り組むべき施策の基本的な方向性は以下のとおりとする。
◯ 学校安全計画・( ① )を見直すサイクルを構築し、学校安全の( ② )性を高める
◯ 地域の多様な主体と密接に( ③ )し、子供の視点を加えた安全対策を推進する
◯ 全ての学校における実践的・( ② )的な( ④ )を推進する
◯ 地域の災害リスクを踏まえた実践的な( ⑤ )・訓練を実施する
◯ 事故情報や学校の取組状況などデータを活用し学校安全を「( ⑥ )化」する
◯ 学校安全に関する意識の向上を図る(学校における( ⑦ )の醸成)
Ⅱ 学校安全を推進するための方策
学校安全に関する( ⑧ )的取組の推進、家庭、地域、関係機関等との( ③ )による学校安全の推進、学校における( ④ )の充実、学校における( ⑨ )の取組の充実等に関し具体的な取組を進めることにより、学校安全に関する取組の推進と学校安全に関する社会全体の意識の向上、すなわち、学校における( ⑦ )の醸成を図るものとする。
1.学校安全に関する組織的取組の推進
(1)学校経営における学校安全の明確な位置付け
学校安全に関わる活動を校内全体として行うためには、( ④ )・( ⑨ )を担当する教職員にその重要性や進め方が共通理解されていることが大切である。( ⑩ )のリーダーシップの下、学校安全計画に基づく学校全体としての活動や適切な役割分担に基づく事故・災害等発生時の対応ができるよう校内体制が整えられている環境下でなければ、( ② )的な取組を進めることは困難である。
このため、( ⑩ )が学校安全を学校経営に明確に位置付けることや、学校安全計画に基づく( ⑧ )的・計画的な活動を進められる環境が整えられるよう( ⑪ )を設置すること等により、学校安全に関する切な役割分担と共通理解に基づく対応ができる校内体制を設けることが重要である。
3.学校における安全に関する教育の充実
学校における( ④ )の目標は、日常生活全般における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の( ⑫ )を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力を育成することを目指す(➡︎POINT解説②参照)ものである。
各学校では、新学習指導要領において重視している( ⑬ )の考え方を生かしながら、児童生徒等や学校、地域の実態及び児童生徒等の( ⑭ )を考慮して、学校の特色を生かした( ④ )の目標や指導の重点を設定し、( ⑮ )を編成・実施していくことが重要であり、各学校において管理職や教職員の共通理解を図りながら、( ④ )を積極的に推進するべきである。
(2)地域の災害リスクを踏まえた実践的な( ⑤ )の充実
(( ⑤ )の重要性・必要性)
(中略)
( ⑤ )は、単に生命を守る技術の教育として狭く捉えるのではなく、どのような児童生徒等の資質・能力を育みたいのかという視点から「防災を通した教育」と広く捉えることも必要である。( ⑤ )には、災害時に自分と周囲の人の命を守ることができるようになるという効果とともに、児童生徒等の主体性や社会性、( ⑯ )や地域を担う意識を育む効果や、地域と学校が連携して( ⑤ )に取り組むことを通じて大人が心を動かされ、地域の防災力を高める効果も期待される。自然災害に関する教育を行う際には、自然がもたらす恩恵などについて触れることにより、児童生徒等が自身の暮らす地域に対する理解を深めることができるようにすることへの配慮も必要である。
新学習指導要領において「( ⑰ )」の実現を図ることとされる中、( ⑤ )についても、地域の( ⑱ )などの資格者やボランティアなどの人材、公民館における防災講座なども教育資源として活用することが重要である。( ⑲ )と学校の連携のみならず、地域に密着して「( ⑳ )」の役割を担っている消防団、自主防災組織、自治会やまちづくり組織等の地域コミュニティの活動と、学校における( ⑤ )を関連付けることや、防災・減災に専門性を持つ大学・NPO等が学校における( ㉑ )をはじめとする( ⑤ )に参画するなど、地域の実情に応じた( ⑤ )を進めることも重要である。
①危機管理マニュアル ②実効 ③連携・協働 ④安全教育 ⑤防災教育 ⑥見える ⑦安全文化 ⑧組織 ⑨安全管理 ⑩校長 ⑪校内安全委員会 ⑫生命尊重 ⑬カリキュラム・マネジメント ⑭発達の段階 ⑮教育課程 ⑯郷土愛 ⑰社会に開かれた教育課程 ⑱防災リーダー ⑲消防署 ⑳共助 ㉑避難訓練
POINT解説②子どもの主体性を重視した計画
「第3次学校安全の推進に関する計画」は現行の学習指導要領に沿う形で策定されています。そのため、目指す姿として「全ての児童生徒等が、自ら適切に判断し、主体的に行動できるよう、安全に関する資質・能力を身に付けること」を掲げるなど、子どもの主体性を重視した計画になっています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。