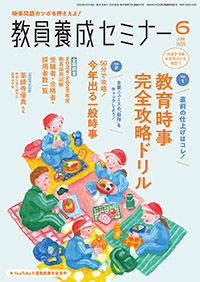第2章 教師を取り巻く環境整備の基本的な考え方
1.「令和の日本型学校教育」を担う教師及び教職員集団の姿
⑴ 学びに関する( 1 )としての教師
(中略)
◯教師の在り方については、これまでも中央教育審議会で議論が重ねられてきた。例えば、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)」(平成24(2012)年8月28日中央教育審議会)においては、教師に求められる力として大きく3点で整理された。
①教職に対する( 2 )、( 3 )力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力(使命感や 2 、教育的愛情)
②専門職としての高度な知識・技能(教科や教職に関する高度な専門的知識、新たな学びを展開できる( 4 )、教科指導・( 5 )・学級経営等を的確に実践できる力)
③総合的な人間力(豊かな( 6 )や社会性、( 7 )力、同僚と( 8 )で対応する力、地域や社会の多様な組織等と( 9 )できる力)
(中略)
◯具体的には、教師自身が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて( 3 )心を持ちつつ主体的に学び続けること、一人一人の教師の個性に即して学校現場の課題に対応するための( 10 )(➡︎POINT解説①参照)学びや、教師同士の学び合いなどを通じた( 11 )(➡︎POINT解説①参照)学びを行うことなどが求められている。また、教師一人一人の専門性を高めることと併せて、学校組織が多様な専門性や背景を持つ人材との関わりを常に持ち続けるとともに、そうした人材を積極的に取り込んでいくことが重要であるとされている。
◯このように、教師は、学びに関する( 1 )であり、教職生涯を通じて( 3 )心を持って主体的に学び続けること、教科や教職に関する高度な専門的知識や新たな学びを展開できる( 4 )、子供の学びの過程を見取り質の高い学習評価を通じて( 12 )につなげていく力量等に加え、教職に対する使命感や( 2 )、子供に対する教育的愛情、豊かな( 6 )や社会性等が求められる。さらに、学校が、直面する様々な教育課題を克服できる組織として進化するために、教職員集団の( 13 )の確保が重要となっている。
第3章 学校における働き方改革の更なる加速化
1.「学校における働き方改革答申」を踏まえた取組状況等
◯「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(平成31(2019)年1月25日中央教育審議会。以下「学校における働き方改革答申」という。)は、
・学校における働き方改革の目的を改めて整理したこと、
・教師の( 14 )管理について、時間は大切なリソースである旨を明確化し、時間の効果的な配分により、子供へのよりよい教育を行うべきという方向性を明示したこと、
・「学校・教師が担う業務に係る( 15 )分類」を策定したこと、
・「教師の( 14 )の上限に関する( 16 )」(以下「上限( 16 )」という。)を策定したこと
など、ともすると、学校教育行政において、これまで必ずしも積極的に議論されてこなかった内容に焦点を当てた答申であった。
第4章 学校の指導・運営体制の充実
1.教職員定数の改善と教職員配置の在り方等
⑵ 持続可能な教職員指導体制の構築
(若手教師への支援の在り方)
(中略)
◯新規採用教師への支援の観点から、新卒1年目は、学級担任ではなく教科担任として( 17 )を担当させたり、( 18 )の軽減を図ったりする取組を行っている教育委員会の例もあり、国においては、このような取組を行うことができるよう、( 19 )制の充実に向けた定数改善を図る必要がある。
第5章 教師の処遇改善
2.教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善の在り方について
⑶ 教職の重要性を踏まえた教師の処遇改善の在り方について
(中略)
◯こうしたことから、今回の処遇改善について、教職がより魅力ある職となるように処遇改善を図り、教師に優れた人材を確保するため、前述したとおり、( 20 )法の趣旨を踏まえ、その他の処遇改善策とあわせて、( 20 )法による処遇改善後の教師の優遇分の水準を確保するため、教師の職務等の特殊性を踏まえ本給相当として支給される( 21 )(➡︎POINT解説②参照)の率については、現在の( 22 )%を少なくとも( 23 )%以上とすることが必要であり、その水準を目指していくべきである。
1. 高度専門職 2. 責任感 3. 探究 4. 実践的指導力 5. 生徒指導 6. 人間性 7. コミュニケーション 8. チーム 9. 連携・協働 10. 個別最適な 11. 協働的な 12. 指導の改善 13. 多様性 14. 勤務時間 15. 3 16. ガイドライン 17. 学級副担任 18. 持ち授業時数 19. 教科担任 20. 人材確保 21. 教職調整額 22. 4 23. 10
POINT解説①「個別最適な学び」と「協働的な学び」とは
2021年に出された中央教育審議会の答申において、子どもたちに必要な学びとして示された言葉です。上の本文では、同様の学びが教師においても必要であると述べています。
POINT解説②「教職調整額」とは
教員には時間外手当が支給されないかわりに、「教職調整額」が支給されてきました。給与月額のうち一定の割合を給与に上乗せするというものです。以前は4%とされていましたが、この答申で「10%以上」との提言がなされ、文部科学省と財務省の折衝が行われ、最終的には2030年度までに10%に引き上げることが決まっています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。