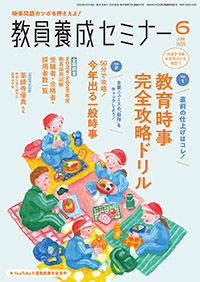1.これからの社会像とこれまでの学習指導要領の趣旨の実現状況
⑴これからの社会像
◯人口減少・( 1 )化や地球環境の有限性を踏まえた持続可能な社会づくり
・一人一人が可能性を開花させなければ国が立ち行かない状況
・資源や環境の有限性を踏まえつつ、環境・福祉と経済を両立していく必要性
・( 2 )存続が現実問題となる中、地域におけるヒト・モノ・カネの循環や幸福・福祉( 3 )(➡︎POINT解説①参照)の向上も喫緊の課題であり、( 4 )を持った社会の創り手を育てる必要性
◯公正な社会における多様な子供たち一人一人の豊かで幸福な人生の実現
・不登校児童生徒や( 5 )教育の対象となる児童生徒、外国人児童生徒など、( 6 )を有する子供を含め、教育的支援を要する子供が増加し、子供たちの多様性が顕在化
・( 7 )など、世帯の経済的困窮等を背景に教育や体験の機会に乏しく、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にある子供たちの存在
・こうした多様な子供たちを学校教育の中で包摂し、特定分野に突き抜けた興味や関心を示したり( 6 )を有する子供等も含め、一人一人の強みを伸ばしつつ、より良く資質・能力を育んでいくことにより、豊かで幸福な人生を送ることができるようにすることが重要
◯グローバルな協働
・グローバルな競争が進む中にあって、国内外で異なる( 8 )を持った人々と、協働による課題解決も求められる。一方、国際的な( 9 )や対立等も鮮明となっており、インターネットやSNSを通じてアルゴリズムで選別された自分の好む情報のみを取得することになる現象( 10 、エコーチェンバー)がそうした( 9 )や対立を加速化させているとの見方もある。
◯生成AIの加速度的発展など変化の加速化・( 11 )化
・生涯に亘って学び続ける資質・能力がこれまで以上に重要に
・テクノロジーと( 12 )な社会の実現が重なる部分で価値を生み出せる社会へ
・既存の情報を整理・分析するだけならAIの方が有能。AIやデータを十全に使いこなすことは前提としつつ、豊かな人間性を育むこと、個々の情報の意味を理解し問題の本質を問うこと、課題を発見したり設定したりすることの重要性が高まる
・そうした中で得られる質の高い知識が社会をよりよい方向に革新していく重要な基礎や基盤となる
(中略)
⑵現行学習指導要領の目指したものとその趣旨の実現状況
◯現行学習指導要領は⑴のような時代状況を一定程度踏まえて改訂されたものであり、以下のような( 13 )と( 14 )のコンセプトは優れており、現在においても概ね妥当との意見。
・「生きる力」の理念や「( 15 )」の学習過程に関する考え方
・学力観を「( 16 )」中心から「資質・能力」を基盤としたものへと拡張
・「資質・能力」の育成に向けた授業改善の視点として「主体的・対話的で深い学び」を提起
・深い学びの視点を契機に、知識相互の関連や概念形成に言及し、「( 17 )」の考え方を提起
・各教科等の「( 18 )」の提起により、各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方を明らかにし、各教科等を学ぶ本質的な意義を明確化
・「( 19 )教育課程」の理念により、社会の変化に目を向け、それを柔軟に受け止めつつ、求められる教育課程の在り方を不断に探究し続けることの重要性を提起
・「( 20 )・マネジメント」の考え方を打ち出し、( 20 )を改善し続けることの意義とその方向性を明確化
◯「主体的・対話的で深い学び」に取り組んだ児童生徒は、社会経済的背景が低い状況にあっても、各教科の正答率が高い、( 21 )が高いといった傾向。
◯現場の授業改善に一定の効果が見られているが、知識の概念としての理解や、自分の考えや根拠等を説明するといった「( 22 )」の育成には課題も見られるとの調査結果。
◯PISA2022では、世界トップレベルの学力を維持し、社会経済文化的背景による学力の格差が小さい国の一つであるとの評価も受けているが、感染症等により再び休校になったときに( 23 )的に学習を行う自信が低いといった状況も見られる。
⑶現行学習指導要領の実施上の課題
(検討すべき方策)
(中略)
◯教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合う必要性はあるが、その負担感がどのような構造により生じているのか精緻に議論すべき。その際、教師の「( 24 )」と、いわゆる「( 25 )」(➡︎POINT解説②参照)との呼称で指摘されている諸課題は区別して議論し、学習指導要領や同解説の在り方に加え、厚い教科書・入試の影響・教師用指導書も含めた授業づくりの実態などを全体として捉えて対応し、教育課程の実施に伴う過度な負担感が生じにくい仕組みを検討すべき
1. 少子高齢 2. コミュニティ 3. well-being 4. 当事者意識 5. 特別支援 6. 特異な才能 7. 子供の貧困 8. 価値観 9. 分断 10. フィルターバブル 11. 非連続 12. 持続可能 13. 前文 14. 総則 15. 習得・活用・探究 16. 内容 17. 知識の質 18. 見方・考え方 19. 社会に開かれた 20. カリキュラム 21. 自己有用感 22. 思考力、判断力、表現力等 23. 自律 24. ワーク・オーバーロード 25. カリキュラム・オーバーロード
POINT解説①「well-being(ウェルビーイング)」とは
「肉体的・精神的・社会的にすべてが満たされた状態」を指す言葉として、最近になって教育界でも使われるようになりました。幸福度をGDPだけで計ることへの問題提起として、登場した側面もあります。
POINT解説②「カリキュラム・オーバーロード」とは
直訳すると「教育課程の過積載」で、教育内容が多すぎて学校教育のさまざまなところに歪みが生じている状況を指す言葉です。一方、「ワーク・オーバーロード」は教員の過重労働を意味する言葉です。関連性の深い概念ですが、ここでは「区別して議論」すべきと指摘しています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。