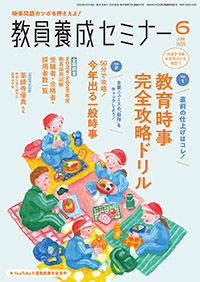第1章 学校教育における人権教育の改善・充実の基本的考え方
1.人権及び人権教育
(2)人権教育とは
(中略)
これらを踏まえれば、人権教育(➡︎POINT解説①参照)の目的を達成するためには、まず、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び、その内容と意義についての( ① )を徹底し、深化することが必要となる。また、人権が持つ価値や重要性を( ② )的に感受し、それを( ③ )的に受けとめるような感性や感覚、すなわち( ④ )を育成することが併せて必要となる。さらに、こうした( ① )と( ④ )を基盤として、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を向上させること、そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成することが求められる。
(3)( ④ )とは
( ④ )とは、人権の価値やその重要性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている状態を感知して、これを望ましいものと感じ、反対に、これが侵害されている状態を感知して、それを許せないとするような、( ⑤ )的な感覚である。「( ⑤ )的な感覚」とは、人間にとってきわめて重要な価値である人権が守られることを肯定し、侵害されることを否定するという意味において、まさに価値を志向し、価値に向かおうとする感覚であることを言ったものである。このような( ④ )が健全に働くとき、自他の人権が尊重されていることの「妥当性」を肯定し、逆にそれが侵害されることの「問題性」を認識して、( ⑥ )を解決せずにはいられないとする、いわゆる( ⑦ )が芽生えてくる。つまり、( ⑤ )的な( ④ )が知的認識とも結びついて、問題状況を変えようとする( ⑦ )又は意欲や態度になり、自分の人権とともに他者の人権を守るような( ⑧ )に連なると考えられるのである。
(4)人権教育を通じて育てたい資質・能力
このように見たとき、人権教育は、人権に関する( ① )と( ④ )の涵養を基盤として、意識、態度、実践的な行動力など様々な資質や能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教育であることがわかる。
このような人権教育を通じて培われるべき資質・能力については、次の3つの側面(1.( ⑨ )側面、2.( ⑩ )側面及び3.( ⑪ )側面)から捉えることができる。
第2章 学校における人権教育の指導方法等の改善・充実
第1節 学校としての組織的な取組と関係機関等との連携等
1.学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進
(2)人権教育の充実を目指した教育課程の編成
(中略)
【参考】教育課程の編成に当たっての留意点
1.「( ⑫ )の教育力」を活用する
各教科等の特質に応じて、( ⑫ )のひと・もの・ことや施設等、( ⑫ )の教育力を計画的・効果的に活用して、教育活動全体を通して人権教育を推進する。
2.「( ⑬ )的な活動」を取り入れる
フィールドワークなどの( ⑬ )活動を積極的に活用して、人権についての「関心・意欲・態度」、「思考・判断」、「技能・表現」、「知識・理解」を育て、( ④ )を育成する。
3.学習形態、教育方法上の工夫を行う
児童生徒の実態を踏まえ、人権教育の目的に応じて、計画的に、一斉学習・( ⑭ )学習・( ⑮ )学習などの学習形態の工夫を行う。また、目的・内容に応じて、授業担当教員とゲストティーチャー(( ⑫ )人材等)とのティーム・ティーチングを取り入れたり、コンピュータなどの( ⑯ )を活用したりするなど、指導形態・方法の工夫を行う。
4.「生き方学習」や進路指導と関わらせる
学級活動や( ⑰ )活動などでの人間としての在り方生き方についての自覚を深める学習や、( ⑱ )の機会等を通して長期的・広域的視野から人権教育を推進する。
(3)人権尊重の理念に立った生徒指導
学校における生徒指導は、個々の児童生徒の( ⑲ )(➡︎POINT解説②参照)を伸ばす積極的な面にその本来の意義があり、全ての児童生徒の( ⑳ )のよりよき発達を目指すとともに、学校生活が、児童生徒一人一人にとって、また、学級や学年、学校全体といった集団にとっても、充実したものとなるようにすることを目的としている。この点において、生徒指導の活動は、[自分の( ㉑ )さとともに他の人の( ㉑ )さを認めること]ができる( ④ )を育成し、学校において、一人一人の児童生徒が( ㉑ )にされることを目指す人権教育の活動とも、互いに相通ずるものということができる。
生徒指導の取組に当たっては、学業指導、( ㉒ )指導、社会性指導、余暇指導、健康安全指導などその指導の全体を通じ、児童生徒一人一人の自己実現を支援し、( ㉓ )・問題解決能力を育成するとともに、併せて、( ④ )の涵養を図っていくことが期待される。
①知的理解 ②直感 ③共感 ④人権感覚 ⑤価値志向 ⑥人権侵害 ⑦人権意識 ⑧実践行動 ⑨知識的 ⑩価値的・態度的 ⑪技能的 ⑫地域 ⑬体験 ⑭グループ ⑮個別 ⑯情報機器 ⑰ホームルーム ⑱進路指導 ⑲自己指導力 ⑳人格 ㉑大切 ㉒個人的適応 ㉓自己指導能力
POINT解説①なぜ今、人権教育か
この資料が出されたのは17年も前になりますが、今も多くの自治体が出題しています。背景には、外国人児童生徒の増加があり、多様な価値観や文化をもつ人々との協働が求められる中で、この資料が注目を集めているのだと考えられます。
POINT解説②「自己指導(能)力」とは
聞きなれない言葉ですが、2022年に改訂された『生徒指導提要』にも登場します。『生徒指導提要』では、「深い自己理解に基づき、『何をしたいのか』、『何をするべきか』、主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・設定して、この目標の達成のため、自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力」と定義されています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。