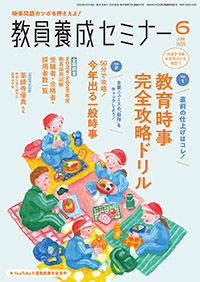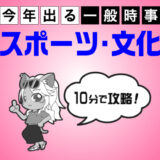●【その1】からのつづき(※カッコ内の数字は【その1】からの続き数字となります)
2.これからの社会像や現状の課題を踏まえた資質・能力
(中略)
⑵学習の基盤となる資質・能力
◯言語能力、( 26 )、問題( 27 )・解決能力といった「学習の基盤となる資質・能力」については重複する部分も多く、現場の具体的な実践に繋がっていない場合もある。
(中略)
◯このうち特に( 26 )については、生成AIの加速度的発展により( 28 )(➡︎POINT解説③参照)のリアリティが増す中、教育課程全体での扱いに加え、各教科等を通じた具体的な充実方策も併せて検討すべき。その際、( 26 )の向上とそれによる探究的な学びの充実を一体的に考えていくべき。
⑶学校における( 29 )学習基盤の整備を踏まえた学びの在り方
◯手軽に回答を得られる( 29 )時代であるからこそ、人間中心の発想で生成AI等を使いこなしていくためにも、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」といった各教科等で身に付ける資質・能力が一層重要となるという認識に立ち、( 30 )の充実をはじめとして、( 29 )とリアルのバランスを取りながら資質・能力の育成に取り組むことに留意が必要。
◯GIGAスクール構想の下、( 31 )環境やアクセシビリティ機能を含む( 29 )学習基盤を効果的に活用している学校では、多様な子供たちを包摂する実践が進むとともに、多様な教材の活用や思考過程の可視化などにより、( 32 )な学びと( 33 )な学びが促進され、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善が進んでいる例も見られている。一方で、従前からの指導においても同様であるが、育成すべき資質・能力を十分に意識しない実践が行われることにより、( 34 )等のツールが先に述べたような役割を果たすことなく、「( 35 )学び」に繋がっていない例も見られることに留意する必要。
◯( 29 )学習基盤は、今後の学習者主体の学びを支える極めて重要なインフラである。このため、教師の指導のツール(教具)としての側面のみならず、学びやすさの提供や( 36 )の基盤であることなど、学習者のためのツール(( 37 ))という側面にも十分な目配せをして、課題に向き合いつつ積極的な活用を推進することが重要。
3.各教科等の目標・内容、方法、評価
(中略)
⑵学習評価の現状と育成すべき資質・能力を踏まえた今後の対応
(現状)
◯資質・能力の育成につながるよう学習評価の質を高めていくことは、教師の38 や授業改善に直結するものであり、「指導と評価の( 39 )」を一層進めることが重要。
◯学習評価を「知識・技能」「思考・判断・表現」「( 40 )」の3観点で行うこととした現行の( 41 )評価は、授業改善に重要な役割を果たすものである一方、特に「( 40 )」の観点については、「( 42 )」の意味が具体的に整理されていないこともあり、依然としてノート提出の頻度などの「勤勉さ」の評価に留まっている学校もある。
4.多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する柔軟な教育課程
(中略)
⑵教育課程の柔軟性の在り方
(教育課程の編成・実施の柔軟性)
◯多様な個性・特性を有する子供たちに応じた適切な支援・指導を行う観点から、
・学校が教育課程を編成する際の柔軟性
・子供一人一人に応じて教育課程を実施する際の柔軟性の両面から具体的な方策を検討すべき。
◯学校の教育課程編成の柔軟性の視点からは、現行の教育課程の特例制度( 43 、 44 、小中一貫、中高一貫など)をより活用しやすくするとともに、各教育委員会の判断や学校のカリキュラム・マネジメントにより、各教科等の標準授業時数についてどのような柔軟性を持たせられ得るのかなど、各学校の教育課程編成に係る教育委員会(学校)の裁量拡大の在り方について検討すべき。(例えば、①午前は教科等の授業を実施し、午後は( 45 )や教科・領域に該当しない多様な学びを重点的に実施する取組、②( 26 )に係る時間を創設して各教科等の情報教育に関連する内容をまとめて指導するといった取組も行われており、こうした柔軟な取組をより行いやすくするためにどのようなことが考えられるか。)
◯年間の最低授業週数(35週以上)や、( 46 )(小学校1単位時間45分、中学校1単位時間50分)(➡︎POINT解説④参照)については、現在でも学校に裁量が認められているが、当該規定が硬直的な教育課程編成を助長しているとの指摘もあり、取扱いを検討すべき。
◯子供一人一人に応じた教育課程の実施の柔軟性の観点からは、子供が興味・関心や( 47 )に応じて自ら教材・方法・( 48 )等を選択できることを改めて整理しつつ、どのような実施上の課題があるのか丁寧に検討し、示していくことが考えられる。
26. 情報活用能力 27. 発見 28. Society5.0 29. デジタル 30. 体験活動 31. クラウド 32. 個別最適 33. 協働的 34. ICT 35. 深い 36. 合理的配慮 37. 文房具 38. 力量形成 39. 一体化 40. 主体的に学習に取り組む態度 41. 観点別 42. 主体性 43. 教育課程特例校 44. 授業時数特例校 45. 探究学習 46. 単位授業時間 47. 能力・特性 48. ペース
POINT解説③「Society5.0」とは
狩猟社会(Society1.0)、農耕社会(Society2.0)、工業社会(Society3.0)、情報社会(Society4.0)に続く新たな社会として国が目指している姿。「第5期科学技術基本計画」において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」と定義されています。
POINT解説④「単位授業時間」とは
小学校は45分授業、中学校・高校は50分授業というのがスタンダードになっていますが、この「単位授業時間」は学校裁量で崩すことが可能です。例えば、小学校であれば15分のモジュール授業を3回行うことで、1単位授業時間とカウントすることができます。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。