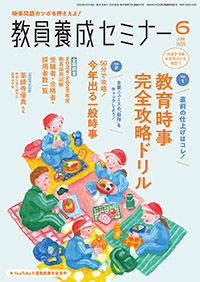第Ⅰ部 総論
1.急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力
◯ 人工知能(AI)、( ① )、Internet of Things(IoT)、( ② )等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられたSociety5.0時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものがこれまでとは「( ③ )」と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。
(中略)
◯ このように急激に変化する時代の中で、我が国の学校教育には、一人一人の児童生徒が、自分のよさや( ④ )認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と( ⑤ )しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、( ⑥ )の創り手となることができるよう、その資質・能力を育成することが求められている。
3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿
(中略)
◯ その際、従来の社会構造の中で行われてきた「( ⑦ )」や「( ⑧ )」(➡︎POINT解説①参照)への偏りから脱却し、本来の日本型学校教育の持つ、授業において子供たちの思考を深める「( ⑨ )」を重視してきたことや、子供一人一人の( ⑩ )と向き合いながら一つのチーム(目標を共有し活動を共に行う集団)としての学びに高めていく、という強みを最大限に生かしていくことが重要である。
◯ 誰一人取り残すことのない、持続可能で( ⑩ )と包摂性のある社会の実現に向け、学習指導要領前文において「( ⑥ )の創り手」を求める我が国を含めた世界全体で、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組んでいる中で、ツールとしてのICTを基盤としつつ、日本型学校教育を発展させ、2020年代を通じて実現を目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」と名付け、まずその姿を以下のとおり描くことで、目指すべき方向性を社会と共有することとしたい。
(1)子供の学び
◯ 我が国ではこれまでも、学習指導要領において、子供の( ⑪ )を生かした自主的、主体的な学習が促されるよう工夫することを求めるなど、「( ⑫ )指導」が重視されてきた。
(中略)
◯ 全ての子供に基礎的・基本的な⑬ を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を( ⑭ )しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供一人一人の( ⑮ )や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「( ⑯ )」が必要である。
◯ 基礎的・基本的な( ⑬ )等や、言語能力、情報活用能力、( ⑰ )等の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じての( ⑱ )から得た子供の( ⑪ )・キャリア形成の方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子供自身が学習が最適となるよう( ⑭ )する「( ⑲ )」も必要である。
◯ 以上の「( ⑯ )」と「( ⑲ )」を教師視点から整理した概念が「( ⑫ )指導」であり、この「( ⑫ )指導」を学習者視点から整理した概念が「( ⑳ )」である。
(中略)
◯ さらに、「( ⑳ )」が「孤立した学び」に陥らないよう、これまでも「日本型学校教育」において重視されてきた、探究的な学習や( ⑱ )などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と( ⑤ )しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、( ⑥ )の創り手となることができるよう、必要な資質・能力を育成する「( ㉑ )」を充実することも重要である。
4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性
◯ 家庭の経済状況や地域差、本人の( ⑮ )等にかかわらず、全ての子供たちの( ㉒ )を一体的に育むため、これまで日本型学校教育が果たしてきた、①学習機会と学力の保障、②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障、③安全・安心な居場所・( ㉓ )としての身体的、精神的な健康の保障、という3つの保障を学校教育の本質的な役割として重視し、これを継承していくことが必要である。
(中略)
◯ さらに、( ㉔ )か個別学習か、( ㉕ )主義か( ㉖ )主義(➡︎POINT解説②参照)か、( ㉗ )かアナログか、遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった、いわゆる「( ㉘ )」の陥穽に陥らないことに留意すべきである。どちらかだけを選ぶのではなく、教育の質の向上のために、発達の段階や学習場面等により、どちらの良さも適切に組み合わせて生かしていくという考え方に立つべきである。
①ビッグデータ ②ロボティクス ③非連続 ④可能性 ⑤協働 ⑥持続可能な社会 ⑦正解主義 ⑧同調圧力 ⑨発問 ⑩多様性 ⑪興味・関心 ⑫個に応じた ⑬知識・技能 ⑭調整 ⑮特性 ⑯指導の個別化 ⑰問題発見・解決能力 ⑱体験活動 ⑲学習の個性化 ⑳個別最適な学び ㉑協働的な学び ㉒知・徳・体 ㉓セーフティネット ㉔一斉授業 ㉕履修 ㉖修得 ㉗デジタル ㉘二項対立
POINT解説①「同調圧力」とは
この答申で示された後、「第4期教育振興基本計画」や「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」にも登場した言葉です。日本の学校では、子どもたちが「みんなで同じことを、同じように」することを過度に要求されている点を課題として指摘しています。
POINT解説②「履修主義」と「修得主義」
所定の教育課程を一定年限の間に履修することでもって足りるとするのが「履修主義」、履修した内容に照らして一定の学習の実現状況が期待されるのが「修得主義」です。本答申では、この2つを適切に組み合わせることが重要だと指摘しています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。