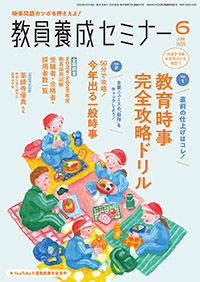第1編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方
1 障害のある子供の教育に求められること
(2)就学に関する新しい支援の方向性
学校教育は、障害のある子供の自立と( ① )を目指した取組を含め、「( ② )」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。そのためにも「( ② )」の形成に向けた( ③ )(➡︎POINT解説①参照)構築のための特別支援教育の推進が必要とされている。
(中略)
そのための環境整備として、子供一人一人の自立と( ① )を見据えて、その時点での( ④ )に最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。このため、小中学校等における通常の学級、( ⑤ )による指導、特別支援学級や、特別支援学校といった、( ⑥ )のある「多様な学びの場」を用意していくことが必要である。
2 早期からの一貫した教育支援
(2)一貫した教育支援の重要性
障害のある子供が、( ⑦ )の一員として、生涯にわたって様々な人々と関わり、主体的に( ① )しながら心豊かに生きていくことができるようにするためには、教育、( ⑧ )、福祉、保健、労働等の各分野が一体となって、社会全体として、その子供の自立を生涯にわたって教育支援していく体制を整備することが必要である。このため、早期から始まっている( ⑨ )・支援を就学期に円滑に引き継ぎ、障害のある子供一人一人の精神的及び( ⑩ )的な能力等をその可能な最大限度まで発達させ、学校卒業後の( ⑦ )に主体的に参加できるよう移行支援を充実させるなど、一貫した教育支援が強く求められる。
3 今日的な障害の捉えと対応
(3)( ⑪ )配慮とその基礎となる環境整備
①( ⑫ )等
(中略)
( ⑬ )第5条においては、「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ( ⑪ )な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」とされており、( ⑪ )(➡︎POINT解説②参照)配慮を的確に行えるようにする環境の整備について、行政機関及び事業者の努力義務とされている。
このような( ⑪ )配慮の基礎となる環境整備については、( ⑫ )と呼ぶこととされている。( ⑫ )は、不特定多数の障害者が主な対象となるものであるが、その整備状況を基に、( ⑭ )及び学校が、各学校の状況に応じて、障害のある子供に対し、( ⑪ )配慮を提供することとなる。
第2編 就学に関する事前の相談・支援、就学先決定、就学先変更のモデルプロセス
第4章 就学後の学びの場の柔軟な見直しとそのプロセス
2 個に応じた適切な指導の充実
障害のある子供一人一人に応じた適切な指導を充実させるためには、各学校や学びの場で編成されている( ⑮ )を踏まえ、( ⑯ )を作成し、各教科等の指導目標、指導内容及び指導方法を明確にして、適切かつきめ細やかに指導することが必要である。
( ⑯ )は、( ⑰ )において、( ⑤ )による指導、特別支援学級、特別支援学校での作成が義務付けられている。また、通常の学級に在籍する障害のある子供等の各教科等の指導に当たっても、( ⑯ )の作成に努めることが示されている。
4 継続的な( ⑨ )の実施
(中略)
また、障害の状態等の変化による、特別支援学校から小中学校等、又は小中学校等から特別支援学校への( ⑱ )については、いずれも、対象となる子供が在籍する校長の思料により、その検討が開始される(学校教育法施行令第6条の3第1項、第12条の2第1項)。このため、小中学校等及び( ⑲ )教育委員会のみならず、特別支援学校及び( ⑳ )教育委員会においても、継続的な就学に関する( ⑨ )を行うための体制の整備が必要である。( ⑳ )及び( ⑲ )教育委員会においては、所管する各学における( ㉑ )等の体制整備や、教育委員会による( ㉒ )チームの派遣や定期的な( ㉓ )等を通じた、各学校への支援が必要である。
また、障害のある子供は、学校に加え、( ㉔ )等で過ごす時間も長い場合があることから、子供の成長や課題等について総合的に把握することができるよう、学校や教育委員会関係者が、日常的に( ㉔ )の事業者等との連携を図ることも、継続的な( ⑨ )を行う上で有用である。
①社会参加 ②共生社会 ③インクルーシブ教育システム ④教育的ニーズ ⑤通級 ⑥連続性 ⑦地域社会 ⑧医療 ⑨教育相談 ⑩身体 ⑪合理的 ⑫基礎的環境整備 ⑬障害者差別解消法 ⑭設置者 ⑮教育課程 ⑯個別の指導計画 ⑰学習指導要領 ⑱転学 ⑲市区町村 ⑳都道府県 ㉑校内委員会 ㉒専門家 ㉓巡回相談 ㉔放課後等デイサービス
POINT解説①「インクルーシブ教育システム」とは
「障害者の権利に関する条約」が提唱している概念です。障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないことを意味します。
POINT解説②「合理的配慮」とは
特別支援教育に関連する教育時事の中でも、特によく問われる用語です。障害のある児童生徒のために学校や設置者が行う「必要かつ適当な変更・調整」のことですが、体制や財政面で均衡を失した負担、過度の負担を課さないものとされています。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。