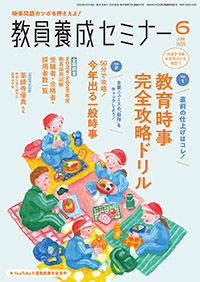はじめに
今日の社会は、生活のあらゆる場面で( ① )を活用することが当たり前の世の中となっている。さらに、人工知能(AI)、( ② )、IoT(Internet of Things)、ロボティクス等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが劇的に変わる「( ③ )5.0」時代の到来が予想されている。
このような時代において次代を切り拓く子供たちには、( ④ )をはじめ、言語能力や数学的思考力などこれからの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力を確実に育成していく必要があり、そのためにも( ① )等を活用して、「公正に( ⑤ )された学び」や学校における( ⑥ )を実現していくことが不可欠である。
しかしながら、我が国の学校における( ① )活用状況は世界から大きく後塵を拝しており、学校の( ① )環境は脆弱かつ( ⑦ )間格差も大きく危機的な状況となっている。
このような状況も踏まえ、今回改訂された学習指導要領においては、初めて「( ④ )」を学習の基盤となる資質・能力と位置付け、( ⑧ )的にその育成を図ることとした。あわせて、その育成のために必要な( ① )環境を整え、それらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしており、情報教育や教科等の指導における( ① )活用など、教育の情報化に関わる内容の一層の充実が図られた。
第1章 社会的背景の変化と教育の情報化
第1節 社会における情報化の急速な進展と教育の情報化
2.「教育の情報化」について
(1) 教育の情報化について
「教育の情報化」とは、( ⑨ )の、時間的・空間的制約を超える、( ⑩ )性を有する、カスタマイズを容易にするといった特長を生かして、教育の質の向上を目指すものであり、具体的には次の3つの側面から構成され、これらを通して教育の質の向上を図るものである。
① 情報教育:子供たちの( ④ )の育成
② 教科指導における( ① )活用:( ① )を効果的に活用した分かりやすく深まる授業の実現等
③ ( ⑪ )の情報化(➡︎POINT解説①参照):教職員が( ① )を活用した情報共有によりきめ細やかな指導を行うことや、( ⑪ )の負担軽減等
あわせて、これらの教育の情報化の実現を支える基盤として、
・教師の( ① )活用指導力等の向上
・学校の( ① )環境の整備
・教育情報( ⑫ )の確保
の3点を実現することが極めて重要である。
第2章 ( ④ )の育成
「( ④ )」は、世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を( ⑬ )したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力である。より具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を( ⑭ )したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり、さらに、このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、( ⑮ )(➡︎POINT解説②参照)、( ⑯ )等に関する資質・能力等も含むものである。
このような( ④ )を育成することは、将来の予測が難しい社会において、情報を( ⑰ )的に捉えながら、何が重要かを( ⑰ )的に考え、見いだした情報を活用しながら他者と( ⑱ )し、新たな価値の創造に挑んでいくために重要である。また、情報技術は人々の生活にますます身近なものとなっていくと考えられるが、そうした情報技術を手段として学習や日常生活に活用できるようにしていくことも重要となる。
第3章 プログラミング教育の推進
第1節 プログラミング教育の必要性及びその充実
2.プログラミング教育の充実
(1)小中高等学校段階を通じたプログラミング教育の充実
(中略)
また、中央教育審議会の議論の土台となった「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)」(中略)では、(中略)プログラミング教育において次のような資質・能力を育むとしている。
【知識・技能】
(小)身近な生活でコンピュータが活用されていることや、問題の解決には必要な( ⑲ )があることに気付くこと。
(中)社会におけるコンピュータの役割や影響を理解するとともに、簡単なプログラムを作成できるようにすること。
(高)コンピュータの働きを( ⑳ )的に理解するとともに、実際の問題解決にコンピュータを活用できるようにすること。
①ICT ②ビッグデータ ③Society ④情報活用能力 ⑤個別最適化 ⑥働き方改革 ⑦地域 ⑧教科等横断 ⑨情報通信技術 ⑩双方向 ⑪校務 ⑫セキュリティ ⑬発見・解決 ⑭整理・比較 ⑮プログラミング的思考 ⑯情報モラル ⑰主体 ⑱協働 ⑲手順 ⑳科学
POINT解説①「校務の情報化」とは
教員の過重労働が問題となる中、校務の情報(デジタル)化を図ることで、負担を軽減することが求められています。中でも、教務・学籍・事務などあらゆる情報を電子化して管理する「統合型校務支援システム」の導入には、大きな期待が寄せられています。
POINT解説②「プログラミング的思考」とは
「プログラミング的思考」については、文部科学省の有識者会議が以下のように定義しています。
「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。