模擬授業には、押さえておくべき「鉄則」と、やってはいけない「NG」があります。練習の段階から、これらを意識しながら授業をするようにしましょう。ここでは、押さえておくべき6つの「鉄則」を紹介します。
※やってはいけない5つの「NG」はこちら。
鉄則1 明るくハキハキと大きな声で話す

「人は見た目が9割」などと言われますが、模擬授業でも第一印象は評価を大きく左右します。少し背伸びをするくらいの気持ちで、「明るく」「ハキハキ」と話し、快活でさわやかな印象を面接官に与えられるように意識しましょう。
鉄則2 教室全体に向けて目線を配る

実際の教師は、30~35人の子どもたちを相手に授業をします。そのため、教室全体をまんべんなく見渡し、子どもたちの様子をよく観察することが求められます。模擬授業でも、意識的に目線を配るようにしましょう。
鉄則3 発達段階を意識して話す

模擬授業では、通常、実施する学年が指定されるので、その学年の発達段階を意識して話すようにしましょう。特に小学校の場合は、低学年と高学年とでは話し方や指示のし方も違ってくるので、注意が必要です。
鉄則4 板書は数色を使い分ける

試験本番で模擬授業を行う環境にもよりますが、チョークはなるべく複数の色を使いたいところです。もちろん、ただカラフルにすればよいというわけではなく、覚えるところは黄色、下線や囲みは赤色といった具合に、ルールを決めて使い分けることが大切です。
鉄則5 適度に「間」を設ける
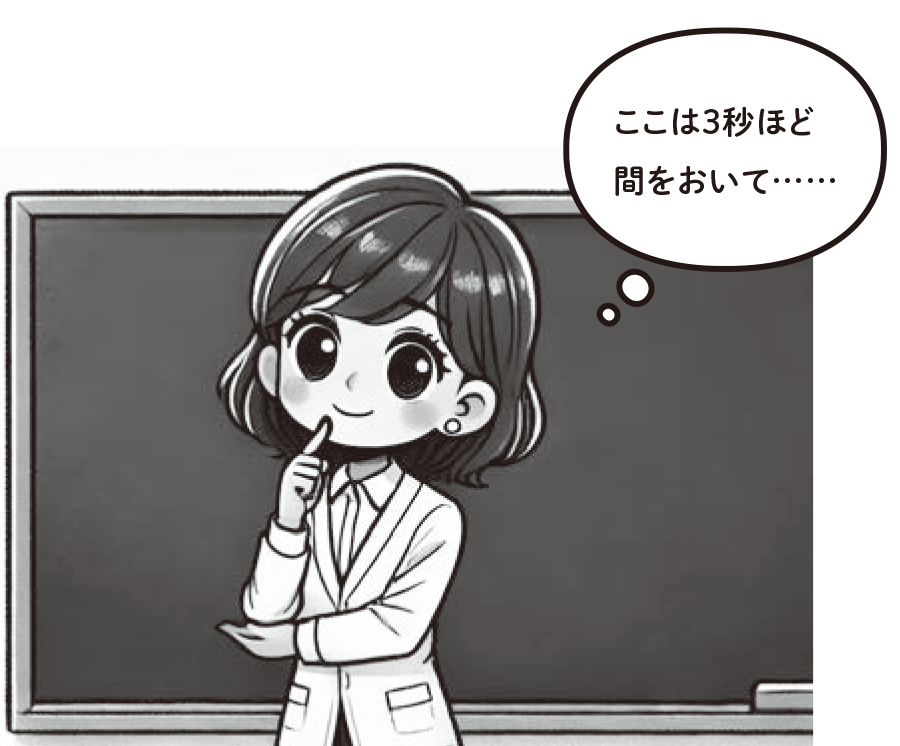
模擬授業は時間が限られているので、つい焦って早口で話し続けてしまいがちです。日ごろの会話もそうですが、ずっと同じテンポで話されると、聞いている側は内容が頭に入ってきづらいものです。適度に「間」を取って、抑揚をつけるようにしましょう。
鉄則6 指示は「1つずつ」「具体的に」する

授業での指示は「1つずつ」「具体的に」することが大事だと言われます。例えば、「教科書を出して、〇ページを開いて、大事だと思うところに線を引いてください」と言うのではなく、「教科書を出してください」と言ってから、「では、38ページを開いてください」と言い、「開けましたか?では、大事だと思うところに線を引いてください」といった具合に、3段階に分けて言うようにしましょう。
※やってはいけない「NG」についてはこちら。
「模擬授業」を詳しく知りたい人は『月刊 教員養成セミナー』2025年5月号をcheck✔
5月号の誌面では、模擬授業の攻略法を詳しく説明するほか、模擬授業の実際例を「誌面実況」でお届けしています。ぜひお手にとってご覧ください。



