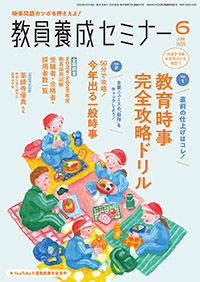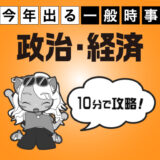●【その1】からのつづき(※カッコ内の数字は【その1】からの続き数字となります)
第一に、より質の高い、深い学びを実現し、資質・能力の育成につながると同時に、分かりやすく、( 24 )学習指導要領の在り方についてです。具体的には、以下の事項などについて御検討をお願いします。
〇 生成AIが飛躍的に発展する状況の下、個別の知識の集積に止まらない概念としての習得や深い意味理解を促すとともに、学ぶ意味、社会や( 25 )とのつながりを意識した指導が一層重要となる中、そうした授業改善に直結する学習指導要領とするためにどのような方策が考えられるか。特に、各教科等の中核的な概念等を中心とした、目標・内容の一層分かりやすい構造化をどのように考えるか。
〇 各教科等の目標・内容の記載に表形式等を活用すること、学校種間・教科等間の関係を俯瞰しやすくすることのほか、デジタル技術を活用した( 26 )やアクセシビリティの向上の観点からどのような工夫が考えられるか。
〇 学習指導要領における重要な理念の関係性をどのように整理すべきか。その際、「主体的・対話的で深い学び」や「個に応じた指導」、「( 27 )と( 28 )の一体的な充実」との関係をどのように考えるか。また、「学習の基盤となる資質・能力」については、 ( 29 )の育成の重要性が高まっていることも踏まえ、どのように整理や明確化を行うべきか。
〇 デジタル学習基盤の活用を前提とした、資質・能力をよりよく育成するための各教科等の示し方についてどのように考えるか。
〇 学習評価について、子供の学習改善や授業改善、教師の力量形成に一層効果的なものとなるよう、評価の観点や頻度、( ㉚ )評価の在り方も含め、どのような改善が必要か。特に、「主体的に学習に取り組む態度」をはじめ観点別学習状況の把握をより豊かな評価につなげるためどのような改善を行うべきか。
第二に、多様な個性や特性、背景を有する子供たちを包摂する( 31 )な教育課程の在り方についてです。具体的には、以下の事項などについて御検討をお願いします。
〇 興味・関心や能力・特性に応じて子供が学びを( 32 )し、教材や方法を選択できる指導計画や学習環境のデザインの重要性、デジタル学習基盤を前提とした新たな時代にふさわしい学びや教師の指導性についてどのように考えるか。
〇 各学校や教育委員会の創意工夫を最大限引き出し、子供一人一人の可能性が輝く( 31 )な教育課程編成を促進する観点から、( 33 )制度や( 34 )制度(➡︎POINT解説③参照)等を活用しやすくすること、各教科等の標準授業時数に係る( 31 )性や学習内容の学年区分に係る( 35 )性を高めることのほか、( 36 )や年間の最低授業週数の示し方についてどのように考えるか。その際、これらが教師に「余白」を生み、教育の質の向上に資する可能性をどのように考えるか。
〇 高等学校の生徒の多様性に応える( 31 )な教育課程の実現のため、( 37 )性を確保しつつ、全日制・定時制・通信制を含め、諸制度の改善をどのように考えるか。
〇 不登校児童生徒や特定分野に特異な才能のある児童生徒など、各学校が編成する一つの教育課程では対応が難しい子供を包摂するシステムの構築に向け、教育課程上の特例を設けること等についてどのように考えるか。
第三に、これからの時代に育成すべき資質・能力を踏まえた、各教科等やその( 38 )についてです。具体的には、子供の学びや生活の実態も踏まえつつ、以下の事項などについて御検討をお願いします。
〇 生成AIをはじめデジタル技術が飛躍的に発展する中、小中高等学校を通じた( 29 )の抜本的向上を図る方策についてどのように考えるか。小学校では各教科等において、中学校では技術・家庭科、高等学校では( 39 )を中心として( 29 )の育成が行われているが、その現状と課題、海外との比較を踏まえた今後の具体的な充実の在り方をどのように考えるか。その際、生成AI等の先端技術等に関わる教育内容の充実のほか、( 40 )や( 41 )の育成強化について教科等間の役割分担を含めどのように考えるか。
〇 質の高い探究的な学びを実現するための「総合的な学習の時間」、「総合的な探究の時間」の改善・充実の在り方をどのように考えるか。その際、( 29 )の育成との一体的な充実や( 42 )的な学びの充実をどのように考えるか。
〇 高等教育段階でデジタル・理数分野への学部転換等の取組が進む中、初等中等教育段階における( 43 )横断・( 43 )融合の観点からの改善についてどのように考えるか。
〇 ( 44 )教育について、小学校高学年の( 44 )科を導入する等、小学校から高等学校まで大幅に充実がなされた中、生成AIの活用を含め、今後の在り方をどのように考えるか。また、手軽に質の高い翻訳も可能となる中、( 44 )を学ぶ意義をどのように考えるか。
〇 教育基本法、学校教育法等に加え、( 45 )法の趣旨も踏まえつつ、国家や社会の( 46 )として、主体的に( 47 )するための教育の改善についてどのように考えるか。
(中略)
〇 ( 48 )システムの充実に向け、合理的配慮の提供を含め、障害のある子供たち一人一人の( 49 )に応じた、質の高い特別支援教育の在り方をどのように考えるか。その際、特別支援学級や( 50 )による指導に係る特別の教育課程の質の向上、自立活動の充実や小中高等学校に準じた特別支援学校での改善方策をどのように考えるか。
〇 「( 51 )プログラム」の成果と課題を踏まえつつ、幼児教育では「環境を通して行う教育」が基本であることにも留意し、幼児教育と小学校教育との円滑な接続の改善についてどのように考えるか。また、設置者や施設類型を問わず、幼児教育の質の向上を図る( 37 )的方策についてどのように考えるか。
第四に、教育課程の実施に伴う( 52 )への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策等についてです。具体的には、以下の事項などについて御検討をお願いします。
〇 教育課程の実施に伴う教師の( 52 )や( 52 )感がどのような構造により生じているのか、学習指導要領や解説、教科書、( 53 )の影響、教師用指導書も含めた授業づくりの実態等を全体として捉えた上で、教育課程の実施に伴う過度な( 52 )や( 52 )感が生じにくい在り方をどのように考えるか。
〇 年間の( 54 )(➡︎POINT解説④参照)を現在以上に増加させないことを前提としつつ、その在り方についてどのように考えるか。あわせて、現代的な諸課題を踏まえた様々な教育の充実について、教育課程の実施に伴う( 52 )への指摘等に留意しつつ、どのように考えるか。
〇 教科書の内容が充実し分量が増加した一方、網羅的に指導すべきとの考えが根強く存在し、( 52 )や( 52 )感を生んでいるとの指摘がある中で、新たな学びにふさわしい教科書の内容や分量、( 55 )等の在り方をどのように考えるか。
(中略)
〇 「社会に開かれた教育課程」を持続可能な形で実現できるよう、( 56 )を含む地域や家庭との連携・協働を促進しつつ、過度な( 52 )を生じさせずに( 57 )を実質化することについてどのように考えるか。
24. 使いやすい 25. キャリア 26. ユーザビリティ 27. 個別最適な学び 28. 協働的な学び 29. 情報活用能力 30. 形成的・総括的 31. 柔軟 32. 自己調整 33. 教育課程特例校 34. 授業時数特例校 35. 弾力 36. 単位授業時間 37. 共通 38. 目標・内容の在り方 39. 情報科 40. 情報モラル 41. メディアリテラシー 42. 教科等横断 43. 文理 44. 外国語 45. こども基本 46. 形成者 47. 社会参画 48. インクルーシブ教育 49. 教育的ニーズ 50. 通級 51. 幼保小の架け橋 52. 負担 53. 入学者選抜 54. 標準総授業時数 55. デジタル教科書 56. コミュニティ・スクール 57. カリキュラム・マネジメント
POINT解説③「特例校」とは
現行の学校教育法や学習指導要領の枠を超えて、特別のカリキュラムを編成できる学校のことで、文部科学省が指定します。このうち、「授業時数特例校」では、特定の教科の授業時数を最大1割削減し、その分を他教科に振り分けることが可能です。
POINT解説④「標準総授業時数」とは
学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を基礎として、国が定めた授業時数。近年はこれが多すぎるとの指摘があり、「増加させないこと」を前提に、次期学習指導要領の在り方が検討される見通しです。
試験に出る「時事問題」が気になる人は『月刊 教員養成セミナー』2025年6月号をcheck✔
6月号は、まるごと1冊時事特集! 対策としては後回しになってしまいがちな「教育時事」と「一般時事」を、短期間で効率よく学べるように構成。もちろん、今まで学習してきた方も復習や力試しとしてもお使いいただけます。ぜひお手にとってご覧ください。